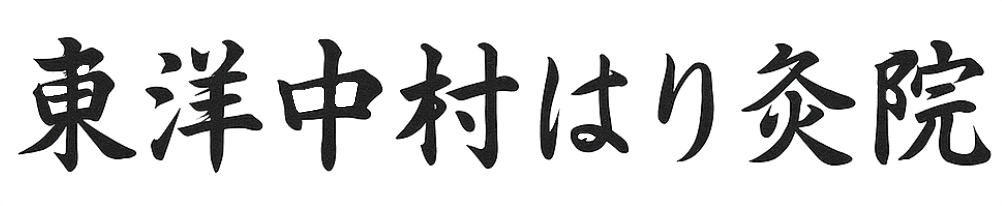繰り返す頭痛の連鎖を
「巡りの改善」で断ち切る
頭が割れるような痛みや締め付けは、首や肩、内臓からの「不通即痛(巡りの滞り)」のサインです。
薬で感覚を麻痺させるのではなく、鍼灸で気血の詰まりを通し、痛みの元を流す。
天気に左右されない、クリアで軽い頭を取り戻しましょう。

目次
頭痛の「不通則痛(滞り)」を解消し、薬に頼らない体質を目指すための東洋医学の診断と治療のすべてを解説します。

東洋医学が考える頭痛の根本原因:
「不通則痛」という大原則
西洋医学では血管や神経の炎症として捉えられがちな頭痛ですが、東洋医学ではその根底に、全身のエネルギーと栄養の「巡り」の滞りがあると捉えます。
これは「不通則痛(ふつうそくつう)—通じざれば則ち痛む」という、東洋医学の痛みの治療における大原則です。
まるで、ダムや川の流れが途中でせき止められ、水圧が上がったり、水が澱んだりしているような状態が、頭の内部で起こっているのです。
-
不通則痛(ふつうそくつう):
頭痛のすべてのタイプに共通する根本原理です。頭部を巡る経絡(けいらく)が、冷えやストレス、栄養不足によって詰まったり、過剰に興奮したりすることで、激しい痛みとして現れます。 -
巡り=気(エネルギー)・血(栄養)・水(体液)の流れ:
頭痛を引き起こす「不通」の状態は、主に以下の三要素の異常な滞りによって生じます。- 気(き):ストレスや緊張によるエネルギーの滞り(パンパンに張る痛み)
- 血(けつ):疲労や冷えによる栄養の不足や滞り(ズキズキと脈打つ痛み、重だるい痛み)
- 水(すい):体内の水液代謝の異常(ズキズキ・重だるい痛み)
-
キーとなる病理要素:
- 瘀血(おけつ):血液のドロドロとした血の滞り。特に慢性的な重く刺すような痛みの原因です。
- 水毒(すいどく):体内の水(体液)の偏りや停滞。頭部の水圧が高まり、むくみを伴う重だるい頭痛や、めまいの原因となります。
-
増悪因子:
季節の変わり目、気圧の変化、急な温度差といった外からの邪気(風寒など)への反応性が高まり、頭痛が誘発されます。

頭痛のタイプ分類(五臓との関連):
あなたの体質的弱点を知る
頭痛は、頭部を巡る経絡(けいらく)がどの「臓腑の乱れ」によって影響を受けているかで分類されます。
この分類(弁証)を行うことで、根本的な治療ターゲットが明確になります。
- 特徴
- 気が上へ突き上げるような痛み。側頭部や目の奥にひびく。
- 随伴症状(サイン)
- 強いストレス、イライラ、睡眠不足の後に出やすい。自律神経の乱れ(肝気鬱結)。
- 代表的なツボ
- 足臨泣/崑崙
- 特徴
- ハチマキを巻いたような頭重感。前頭部にかけて痛む。
- 随伴症状(サイン)
- 首肩こり、便秘傾向、外からの風邪をひきやすい。(気の巡りの停滞)
- 代表的なツボ
- 孔最/瘂門(※深刺し注意)
- 特徴
- 前頭部や顔面、頭全体に重く抜けない痛みが及ぶ。
- 随伴症状(サイン)
- 台風・雨の日前に悪化。頭皮や顔がむくむ(水毒)、食後の倦怠感。
- 代表的なツボ
- 足三里/陰陵泉
- 特徴
- 慢性的な疲労で悪化しやすい。後頭部やうなじに痛みが出る。
- 随伴症状(サイン)
- 冷えで悪化、足は冷えて頭はのぼせる(水火不済)。耳鳴りや夜間頻尿も。
- 代表的なツボ
- 次髎/天柱

鍼灸・漢方のアプローチ:
痛みの土台を変える治療
頭痛治療の要は、痛みを引き起こしている「気・血・水」の巡りの滞り(不通)を解消し、乱れやすい体質そのものを安定させることです。
鍼灸と漢方は、異なる角度からこの体質改善を促します。
鍼灸(経絡治療)の要点
(川の流れを直接改善する)
鍼灸は、気の通り道(経絡)に直接働きかけ、詰まりを解消することで、即効的な巡りの改善と、体質的な機能の底上げを目指します。
-
巡り(気・血・水)の回復:
四診法で体質(肝、脾、腎の乱れ)を見立て、頭に滞っている気・血・水を足元へと導き、全身の巡りを整えます。 -
自律神経と呼吸の調整:
特に肝(ストレス・自律神経)と肺(呼吸・気の巡り)の働きを底上げし、緊張や疲労からくる頭痛の発生を抑えます。
漢方の考え方(体質目安)
(体質の根本から変える)
漢方薬は、患者様の体質に合った生薬の組み合わせにより、体の中から「気・血・水」の生成とバランスを整えます。
-
瘀血(おけつ)傾向:
血の滞りによる痛みには、桃核承気湯(熱と滞り)/加味逍遥散(ストレスと血虚)/桂枝茯苓丸(冷えと滞り)などを用います。 -
瘀血+水毒の複合:
血と水の滞りがある方には、当帰芍薬散など、両方を改善する処方を検討します。 -
水毒(すいどく)傾向:
雨や気圧で悪化する頭痛には、五苓散など、余分な水(水毒)を排出する処方が用いられます。
※漢方薬は症状や体質によって複雑に選ばれます。上記は体質タイプと処方の関連性を示す一例です。

西洋医学との比較とメリット:
頭痛の「体質的な土台」を変える
頭痛に対する西洋医学のアプローチは薬による「痛みの遮断・緩和」が中心です。
一方、東洋医学は「痛みが起きる体質の土台」そのものを変えることに価値があります。
東洋医学が頭痛治療で選ばれる理由
- 検査で原因が捉えにくい頭痛にも対応: 病院でCTやMRIなどの画像検査では異常が見つからない(機能性頭痛など)場合、東洋医学では「気・血・水」の巡りの乱れという体質から根本原因を捉え、アプローチします。
- 四診法で全身像を把握し、個々に合わせた施術: 頭痛の原因が「肝の気の滞り(ストレス)」か「脾の水の偏り(水毒)」かなど、四診法(舌・脈・腹など)で全身の状態を緻密に把握します。頭痛の種類が同じでも原因は人それぞれであるため、個々に最適な選穴・刺激量で効果を最大化します。
- 薬に頼りすぎない根本アプローチ: 痛みを抑える薬は「一時的なダムの決壊を防ぐ」には有効ですが、ダムの構造(体質)までは変えられません。鍼灸は、めぐり(不通則痛の解消)と自律神経(肝の働き)の調律を重視し、「痛みが起きにくい体のリズム」を内側から築きます。

セルフケアと生活の整え方:
頭痛が起きにくい「体質」を作る
鍼灸治療の効果を最大化し、頭部の気血の滞り(不通)を解消するためには、日々の生活習慣が鍵となります。
特に肝・脾・腎といった、頭痛と深く関わる五臓を労わる意識を持ちましょう。
生活習慣のポイント
-
呼吸・瞑想で「気滞」を解消:
肩が上がらない深い腹式呼吸や瞑想は、ストレス(肝)による気の滞りを解消し、神経の過敏化を鎮める最良のセルフケアです。 -
ストレッチで「血」の巡りを改善:
頭痛の多くは首や肩の気血の滞り(瘀血・気滞)から生じます。こわばりをほぐすストレッチで、頭部への不要な緊張を解放しましょう。
長時間の画面作業は適宜区切り、血流の悪化を防ぎます。 -
眼の休憩で「肝」を労わる:
東洋医学では「肝は目に開く」とされ、目の酷使は肝の血(けつ)を消耗し、頭痛を招きます。20分ごとに視線を遠くへ移し、目を休ませましょう。 -
食と睡眠で「気血」を生成・回復:
体を冷やさない温かい和食中心の食事で、気血の生成(脾の働き)を助けます。
特に深夜1〜3時(肝の時間)は、肝が血を貯蔵し、回復に専念する時間です。この時間に眠ることで、頭痛の再発を防ぎます。
ツボ習慣で巡りを促す
以下のツボをやさしく指圧したり温めたりする習慣をつけましょう。
-
三陰交(さんいんこう):
足の内くるぶしから指4本分上。下半身の血の巡りを整え、頭に上がった余分な気や水を足元へ導きます。 -
孔最(こうさい):
肘から手首に向かって指4本分下。気の流れ(肺の働き)を整え、肩こりや頭部の緊張をゆるめる作用があります。

ご予約・ご相談

頭痛専門施術の料金と
体質改善を目指す通院ペース
当院の頭痛に対する経絡治療は、痛みの根本である「不通則痛」と体質の偏りを解消することに焦点を当てています。
自由診療(保険外)となりますが、頭痛薬の減量と再発予防という長期的な視点での費用対効果を重視しています。
詳細な問診と東洋医学的診断(四診法)に基づき、頭痛の根本原因(気滞、血虚、水毒など)を特定し、治療計画を立案します。
全身の経絡を調整し、頭部の緊張と全身の巡りを回復。痛みの出にくい体質へ導きます。
効果を最大化する通院ペースの目安
(巡りの回復と体質安定の戦略)
-
導入期(痛みが強く、頻度が高い時期):
週に1~2回の集中治療が必要です。気の滞りと神経の過敏性を早期に鎮静させることに焦点を当てます。 -
安定化期(薬を飲む回数が減ってきた時期):
週に1回のペースで、五臓の機能を根本から立て直し、天候やストレスに揺らがない体質を構築します。 -
維持期(頭痛が気にならなくなった時期):
症状が安定したら、2〜3週間に1回、あるいは月に1回のペースで、再発予防と全身の疲労回復を目的としたメンテナンスを行います。
頭痛の体質改善は「曇り空を晴れにする」ようなものです。初期に集中して雨雲(滞り)を払い、後は晴れ間(良い状態)を維持することで、頭痛のない日常が定着します。
まずは集中的に通院し、早期の症状軽減を目指しましょう。

院長プロフィール

中村 麻人(なかむら あさと)
札幌「東洋中村はり灸院」院長・鍼灸師。
「森を見て木を治す」東洋医学の視点で、肩こり、腰痛をはじめ、生理痛・顔面神経麻痺・潰瘍性大腸炎・耳管開放症など病院で原因不明、治療法がない慢性疾患を中心にはり治療を行っています。