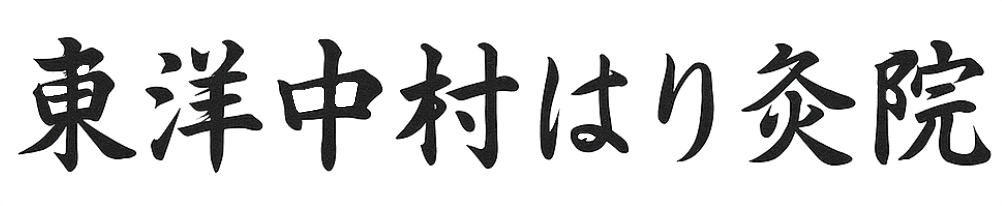胃酸過多症の根本改善
胃の過剰な酸は、「ストレス(肝)」による異常な過熱や「消化機能(脾胃)」の冷えから生じます。
四診法による見立てと経絡治療で、全身のバランスを整え、胃の負担を軽くする。
和の食養生を取り入れ、しみにくい胃、落ち着いた呼吸、安らぐ睡眠へと体質を入れ替えます。
本ページの内容(目次)
薬を飲んでも再発しやすい胃酸過多症を、「胃の異常加熱」という視点から根本的に見直し、体質改善を目指す道筋です。
西洋医学と東洋医学:治療目標とアプローチの決定的な違い
胃酸過多症へのアプローチは、西洋医学と東洋医学でその目標が大きく異なります。西洋医学が「症状の消火」に優れる一方、東洋医学は「火事の起きにくい体質への改善」を担います。
西洋医学(病院)の基本:対症療法の役割
西洋医学は、過剰な胃酸という「目の前の火」を迅速に鎮めることに特化しています。
- 胃酸を抑える対症療法が中心:主に胃酸分泌を強力に抑制する薬(PPI/H2ブロッカーなど)で、一時的に胃酸の生産量を減らし、粘膜の炎症を鎮火します。
- 多因子が示唆される原因:原因はストレスや生活習慣など多岐にわたるとされますが、治療は症状が改善するまで薬を服用するという方法論が一般的です。
- 臓器ごとの専門分化の限界:胃腸の症状は消化器内科、不眠は心療内科、肩こりは整形外科と、臓器ごとに専門が分かれるため、全身のつながりを見落とし、症状別に通院が分散しやすい傾向があります。
東洋医学(当院)の基本:根本改善への道筋
東洋医学は、胃酸の過剰分泌という「異常加熱」を引き起こしている「体質の偏り」そのものに焦点を当てます。
- 体質から整える根本改善を重視:「胃熱(いねつ:胃の異常な熱)」や「肝気鬱結(かんきうっけつ:ストレスによる気の滞り)」という根本原因を解決し、自然治癒力(バランスを元に戻す力)の回復を目指します。
- 全身を総合評価するホリスティックな視点:胃の不調は、自律神経(肝)の乱れ、睡眠不足、冷え(脾虚)など、全身の機能低下と深く連動しています。胃だけでなく、これらすべてを統合して評価・治療します。
- 同じ症状でも原因は人それぞれ:胃酸の多さ(熱証)と胃の機能の弱さ(虚証)では、アプローチが全く異なります。東洋医学は「一人ひとりの体質」を見極め、個別に合わせたオーダーメイドの施術設計を行います。
診断方法の違い:東洋医学の「四診法」で根本原因を浮き彫りに
西洋医学が血液検査や内視鏡で「器質的な異常」を探るのに対し、東洋医学では、症状を引き起こしている「体質の偏り」、すなわち機能的な異常を徹底的に調べます。この見立ての要となるのが、伝統的な四診法です。
四診法(望・聞・問・切):体という地図を読む
四診法は、体全体を一枚の地図のように読み解き、どこで「気の流れ」が滞っているか、どこに「熱」がこもっているかを詳細に把握するための手法です。
- 望診:顔色、皮膚、姿勢に加え、特に「舌」(舌の色、苔の厚さや色、形)を観察します。舌は内臓の状態を映し出す鏡であり、胃の異常な熱(胃熱)や体内の水分代謝の停滞(湿)を正確に把握できます。
- 聞診:声の調子、呼吸の深さ、体から発するにおいなどを把握します。気の勢いや、消化器系に過剰な「熱」がこもっていないかを探ります。
- 問診:現在の症状だけでなく、食事内容、睡眠の質、便や尿の状態、過去の病歴・家族歴まで丁寧に確認します。生活習慣全体から、胃を冷やしたり、ストレスを溜めたりする原因を特定します。
- 切診:脈の速さや強さ、腹部の緊張や冷え、そして全身のツボの反応を触診します。これにより、胃腸の冷え(脾胃の弱り)や、自律神経の過緊張(肝の停滞)といった体質的な根本原因を確定させます。
この緻密な診断により、胃酸過多症の背景にある「脾胃(消化機能)の弱り」「肝(ストレス)の停滞」「肺(呼吸)からの影響」など、胃の不調と全身の複雑なつながりを見立て、最適な治療方針を決定します。
治療手段の違い:鍼灸(経絡治療)による「胃の過熱」の鎮静化
東洋医学の鍼灸治療は、薬で胃酸を強制的に抑えるのではなく、過熱した胃を鎮め、正常な消化機能を取り戻すことを目標とします。全身のバランスを調整し、胃の異常な興奮を鎮めます。
当院の鍼灸(経絡治療):体質の偏りを調整する技術
五臓六腑のバランスは、体表の「経絡(気血の通り道)」に現れます。この経絡の滞りや弱りを調整することで、根本的な改善を図ります。
- 細い鍼・やさしい灸で経絡を整える:髪の毛ほどの細い鍼と、心地よい温和なお灸を使い、気血の通り道(経絡)の詰まりを解消し、乱れた自律神経の働きを調和させます。
-
消化の火力と気の巡りを調整:
- 脾胃(ひい):胃腸の“火力”(消化力)が弱っている場合は底上げし、食べ物をしっかり消化できる力を養います。
- 肝(かん):ストレスによる肝の気のこわばりを緩め、胃への異常な緊張や熱の発生を鎮めます。
- 肺(はい):浅い呼吸(肺の乱れ)からくる横隔膜のこわばりを調整し、逆流を物理的にも防ぎやすくします。
- 痛みや熱さを最小化した設計:治療自体がストレスにならないよう、「心地よさ」を重視した刺激設計を徹底しています。
症状改善に用いられるツボの一例(四診により選穴)
脈やお腹の状態(四診法)によって選ぶツボは異なりますが、特に胃腸の不調に効果的な代表的なツボです。
- 中脘(ちゅうかん)・天枢(てんすう)・足三里(あしさんり):これらは胃腸の機能を直接的に調整する要穴(かなめとなるツボ)です。胃の蠕動運動を正常化させたり、胃腸の冷え(虚)や緊張(実)を緩めたりする働きがあります。
- 孔最(こうさい):呼吸器系のツボですが、自律神経の緊張を緩め、上腹部のこわばりをやわらげる補助的な役割を果たします。
- 温灸による負担軽減:特に腹部の冷えや張りが強い「脾胃虚寒(ひいききょかん)」の体質の方には、じんわり温める温灸を併用し、胃腸の「冷え」という根本原因を優しく取り除きます。
食事・生活アドバイス(食養生):胃の過熱と冷えを防ぐ
鍼灸で体のバランスを整えることはもちろん大切ですが、胃酸過多症の改善には、日々の食養生が治療効果を決定づけます。胃酸の分泌を刺激する要因と、胃を冷やし機能を弱める要因の両方を徹底的に排除しましょう。
基本の考え方:「脾胃の火力」を守る
東洋医学でいう「脾胃(消化機能)」は温かい環境で最も良く働きます。まるで調理をするように、胃を過度に冷やさず、労ることが原則です。
- 胃にやさしい温かい和食中心:消化に負担をかけないよう、汁物、煮物、お粥、柔らかく火を通した根菜など、温かく柔らかい和食を心がけ、胃腸の働きを助けます。
- 胃酸を誘発する食品の制限:冷たい飲食、白砂糖、高脂肪食、香辛料などの刺激物、過度のカフェインやアルコールは、胃酸の分泌を異常に高めたり、胃腸の冷えや湿(よけいな水分)を生んだりするため、控えめにすることが重要です。
- 就寝前の徹底休息:食後すぐに横になると逆流しやすいだけでなく、東洋医学では夜間に胃を働かせると休息を妨げます。就寝2〜3時間前は食事を控え、湯船入浴と腹部・足元の保温で、全身を休息モード(副交感神経優位)に切り替えましょう。
体質に合わせた個別ポイント
同じ胃酸過多症でも、原因が「冷え」か「熱」かで養生が変わります。ご自身の体質に合わせたケアを取り入れましょう。
- 冷え(脾胃虚寒)が強い方:胃腸の働きを助けるため、極端に冷たい飲み物を避け、生姜や大根の穏やかな辛み(胃を温め、気の巡りを促す)を料理に上手に取り入れましょう。
- 張り・逆流感(胃熱・気滞)が強い方:早食いや食べすぎは胃の過剰な緊張と酸分泌を招きます。食事量を小分けにして回数を調整し、一回あたりの胃の負担を減らす工夫が必要です。
- 緊張(肝気鬱結)が強い方:ストレスが原因で呼吸が浅くなり、胸部がこわばっていることが多いです。胸や脇、肩周りの筋肉をゆるめるストレッチや、ゆっくりと呼吸を深めるセルフケアを追加し、胃への圧迫を解放しましょう。
西洋医学との併用について:「即効性」と「体質改善」の両立
胃酸過多症は再燃しやすいため、一時的な症状の緩和だけでなく、根本的な体質の改善が不可欠です。当院では、西洋医学の強みと東洋医学の強みを活かした「ハイブリッドな治療」を強く推奨します。
- 主治医との連携が不可欠:服用中の薬の調整や精密検査は、必ず医師(主治医)の専門的な判断に基づいて行いましょう。東洋医学は西洋医学の治療効果を妨げるものではなく、サポート役として機能します。
-
「即効性の対症療法」と「体質改善」の両輪:
- 病院の薬:「今、炎上している胃の火を鎮める」ための緊急消火活動です。
- 当院の鍼灸:「次に火事が起きにくい地盤(体質)」を作り直すための根本治療です。
- 再燃しにくい体質づくりを支援:鍼灸治療は、薬では難しい睡眠・自律神経(肝)・消化機能(脾胃)のリズムを体の中から整えます。これにより、胃酸の過剰分泌や逆流が起こりにくい「ストレス耐性の高い土台」づくりを支援し、薬に頼らない生活を目指します。
ご予約はこちら
院長プロフィール

中村 麻人(なかむら あさと)
札幌「東洋中村はり灸院」院長・鍼灸師。
「森を見て木を治す」東洋医学の視点で、肩こり・腰痛をはじめ、生理痛・顔面神経麻痺・潰瘍性大腸炎・耳管開放症など病院で原因不明、治療法がない方を中心にはり治療を行っています。