「気・血・水」の調和でととのえる鍼灸|東洋医学の基本をわかりやすく
生命を支える三つの流れ — 滞りをやさしく整え、体の本来の力を引き出す。
東洋医学の基本である「気・血・水」。それぞれの役割と乱れのサイン、鍼灸でどう整えるかをやさしく解説します。
気・血・水とは?
気は生命活動のエネルギー。呼吸・代謝・体温調節・自律神経のはたらきを支えます。
血は全身に栄養を運び、肌や髪、臓腑をうるおし、心を安定させます。
水は体液全般(津液)。関節や粘膜を守り、老廃物の排出を助けます。
“気はめぐりを動かし、血と水は身体を潤す”
— 三つが調和して初めて心身が健やかに保たれます。
滞りが生む不調のサイン
- 気の滞り:息苦しさ、喉のつかえ、疲れやすさ、気分の落ち込み。
- 血の滞り:肩こり、頭痛、生理痛、シミ・くすみ、冷えのぼせ。
- 水の滞り:むくみ、めまい、重だるさ、関節の違和感、天気痛。
東洋医学には「不通則痛(ふつうそくつう)」という考えがあり、流れが滞ると痛みや不調が生じると捉えます。
鍼灸で整える「気・血・水」
鍼は滞りの結び目をやさしく解き、気血の通り道(経絡)をスムーズにします。
灸は冷えや水の偏りを温めて動かし、めぐりを促します。
経絡治療では脈・腹・経絡の反応からアンバランスを読み取り、体質に合わせて刺激量と配穴を設計します。
▶ 東洋医学専門の鍼灸とは|▶ 頭痛|▶ 過敏性腸症候群(IBS)
よくあるご質問
- Q. 自分で気・血・水の乱れを見分けられますか?
A. 目安はありますが、詳細は脈や腹部、舌の所見を合わせて鑑別します。まずはお気軽にご相談ください。 - Q. 整うまでの目安は?
A. 個人差があります。6回〜8回で体の各部で変化を感じる方が多く、体質改善は中長期的に見ます。 - Q. 生活面でできることは?
A. 睡眠リズム、深い呼吸、軽い運動、温める習慣は気血水のめぐりを助けます。個別にアドバイスします。
まとめ・ご相談
「気・血・水」は東洋医学の入口であり、症状を根本から捉える手がかりです。肩こりや疲れやすさなど、ささいなサインも気血水の乱れかもしれません。どうぞ一度ご相談ください。
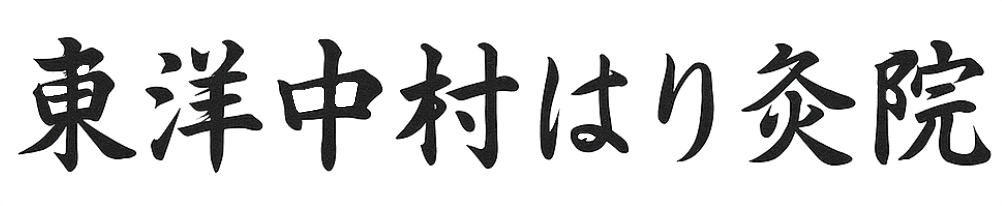
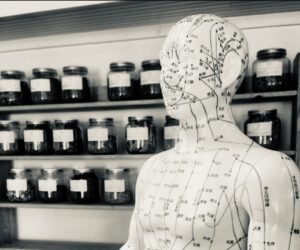


コメント