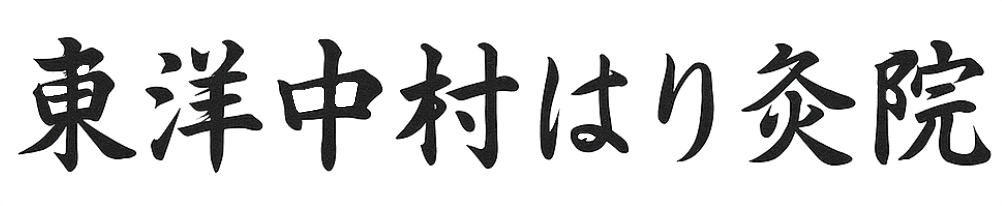潰瘍性大腸炎の症状を抑え、再発を防ぐ 根本からの体質改善
大腸の「山火事」は、全身の「土壌の崩れ」というサインです。
西洋医学による「緊急消火」と東洋医学の「体質強化」を組み合わせ、
炎症が海辺の波のようにぶり返しにくい、安定した体質(寛解)へと導きます。
和食中心の食養生とやさしい鍼灸・漢方治療ではじめる内側からの根本ケア。
本ページの内容(目次):潰瘍性大腸炎の根本改善と体質別の漢方・鍼灸アプローチ
「原因不明」とされてきた潰瘍性大腸炎に対し、東洋医学の専門的な視点から、全身のバランスと「体質の土壌」を整える根本治療の具体的な道筋を解説します。

潰瘍性大腸炎(UC)とは?難病指定の概要・症状・西洋医学の治療法を解説
潰瘍性大腸炎(Ulcerative Colitis, UC)は、現代医学においても原因が未だ特定されていない、大腸の粘膜に慢性的な炎症が起こり続ける炎症性腸疾患(IBD)の一つです。この病気は、日本国内でも患者数が多く、公的な「難病指定」を受けていることからも、その治療と日常生活への影響の大きさがうかがえます。
例えるなら、大腸という大切な「栄養を吸収する土壌」に、まるで山火事が燃え広がったように、炎症(火事)が起き続けている状態です。この火事によって粘膜は深く傷つけられ、びらんや潰瘍(ただれやえぐれた状態)が形成されてしまうのです。
潰瘍性大腸炎の主な症状と特徴的な経過(寛解と再燃)
- 激しい下痢・血便、頻繁な腹痛: 炎症が激しい時期(活動期)には、大腸の機能が著しく低下し、これらの症状が強く現れ、日常の活動を大きく妨げます。
- 全身症状(発熱、貧血、体重減少):慢性的な炎症は体全体を消耗させ、栄養の吸収が妨げられるため、まるで体がマラソンを続けているかのように疲弊し、全身的な症状として現れます。
- 寛解(症状安定)と再燃(症状悪化)の繰り返し: 症状が落ち着く時期(寛解期)と、再び激しく悪化する時期(再燃/活動期)を繰り返します。これは、まるで海辺の波のように、引いては押し寄せる、慢性の経過をたどるのが大きな特徴です。
- 炎症の広がり方: 通常、病変は肛門に近い直腸から始まり、連続的かつ上方へ向かって大腸全体に広がりやすい性質があります。
- 長期経過における合併症リスク: 炎症が長く続くことで、大腸がんなど他の深刻な合併症(狭窄や穿孔など)への定期的な検査と配慮も必要となります。
西洋医学(病院)における潰瘍性大腸炎の認識と主な治療法
西洋医学では、UCは「特定の一つの原因が未解明な病」という認識に基づき、現在の治療は主に症状や炎症を抑える「対症療法」が中心となります。これは、山火事(炎症)が起きた場所へ消火活動をするように、まずは目に見える「火(症状)」を鎮火させることに重点が置かれます。
-
薬物療法:
- 5-ASA製剤(炎症を抑える薬):軽症~中等症の基本的な治療薬として、腸の局所で炎症を抑える働きをします。
- ステロイド(強力な炎症抑制薬):活動期の激しい症状を緊急的に鎮静化するために使用されます。
- 免疫調整薬・生物学的製剤: 自己免疫の過剰な働き(暴走する免疫システム)を調整し、体の内側から炎症のプロセスに働きかける比較的新しくより根本的な制御を目指す治療法です。
- 栄養・食事療法: 炎症で過敏になっている腸への負担を減らし、体力と栄養状態の維持・回復を図るための重要な補助療法です。
- 外科治療(手術): 内科的な薬物治療で炎症の制御が困難な場合や、重篤な合併症(大量出血、穿孔、癌化など)が生じた際には、大腸の全摘出などの手術が最終的な選択肢として検討されることがあります。

潰瘍性大腸炎(UC)を東洋医学・漢方でどう捉える?体質の根本原因と食養生の重要性
東洋医学において、潰瘍性大腸炎(UC)は、単なる大腸という「局所的な場所」の炎症の問題に留まりません。それは、その人が生まれ持った体質の弱さ(体内のバランスの偏り)の上に、不適切な食生活やストレスという「負担」が長期間重なって表面化した、全身の不調のサインと捉えます。
例えるなら、大腸という畑の『土壌』が元々弱っているところに、間違った肥料(食の毒)を与え続け、環境の激変(ストレス)が加わった結果、作物が病気になった状態です。東洋医学の基本姿勢は、炎症を抑える対症療法ではなく、全身の「臓腑(ぞうふ)」のつながり、特に内臓の働きを根本から立て直すことにあります。
潰瘍性大腸炎の根底にある「体質の土壌」:臓腑のつながり
東洋医学では、大腸の不調は五臓六腑(ごぞうろっぷ: 体全体の機能システム)のつながりから、ほかの臓器の弱さと共鳴して現れると考えます。特に以下の臓腑(機能システム)の弱さがUCの根底にある方が多く見られます。
- 「肺(はい)」の弱さ: 呼吸器系だけでなく、皮膚や粘膜、免疫バリア機能を司ります。大腸(粘膜)の弱い方は、呼吸器や皮膚といった外側のバリア機能も弱い傾向があります。
(注:東洋医学では肺と大腸は表裏一体の関係で、どちらかの不調がもう一方に影響しやすいと捉えます。)
- 「腎(じん)」の弱さ: 生命力、免疫力、ホルモンなど、体を根源から支えるエネルギーを司ります。この機能が低下すると、自己治癒力が低下し、慢性的な炎症から抜け出せなくなります。
- 「脾(ひ)」の弱さ: 消化吸収を担う機能システムです。これが弱いと、食べたものが未消化物(『湿』の元)となり、炎症を悪化させます。
共存しやすい「関連症状」の例(体質から生じるサイン)
- 鼻炎・花粉症/喉の不調・咳: 肺と大腸のつながりによる、バリア機能の共通の弱さが現れています。
- 敏感肌・皮膚トラブル、末端冷え: バリア機能の弱さや、体内のエネルギー(気・血)が末端まで届きにくい「冷え」(機能低下)の傾向を示します。
- 生理痛・生理不順など婦人科の悩み: 生命力や血流を司る「腎」や「肝」の機能低下が、腸と婦人科双方に現れます。
- 動悸・浅い眠り(中途覚醒): 体内の過剰な「熱」や「湿」が自律神経を乱し、心の安らぎ(『神(しん)』)が保てない状態です。
悪化の原因となる「食の毒」:湿熱(炎症の元)を生む食品とは?
東洋医学では、症状が激しい活動期には体内に「湿熱(しつねつ)」が充満していると考えます。これは、ドロドロとしたヘドロ(湿)が、熱(炎症)を持って煮えたぎっている状態です。不調な大腸粘膜に対し、特定の食品はこの湿熱を生み出し、まさに山火事(炎症)に油を注ぐような悪影響を及ぼします。
炎症を鎮め、腸の修復を促すためには、まずこの「湿熱を生む毒」を断つ食養生が極めて重要です。
特に避けたい食品と東洋医学的な影響
- 小麦製品(グルテン): グルテンが腸粘膜に負担をかけ、「湿」(ネバネバした病理産物)を生み出す最大の原因となりやすい食品です。(パン、パスタ、ラーメン、ピザ 等)
- 砂糖(精製糖): 腸内で異常発酵しやすく、「湿」や「熱」を急速に生み出し、炎症を激化させます。甘味の強いものは全般的に注意が必要です。(お菓子・清涼飲料・アイス・ケーキ 等)
- 乳製品: 体質によっては過剰な「粘液」を増やし、「湿」をためやすくする作用があります。特に冷たい乳製品は脾胃の負担になります。(牛乳・チーズ・ヨーグルト 等)
- 油(特に酸化した揚げ物): 消化に大きな負担をかけ、消化吸収機能(脾胃)を弱らせ、腸内環境を悪化させ炎症を助長します。
- 体を冷やす食材・冷たい飲食: 冷たい飲食は、消化吸収を担う「脾胃の火(消化力)」を弱め、未消化物を増やし、慢性的な下痢や冷えを招きます。(生野菜サラダ、トマト、キュウリ、パイナップルなど。加熱調理することで緩和されます。)

潰瘍性大腸炎の根本的な改善方法:鍼灸治療と再発を防ぐ体質入れ替えの養生法
東洋医学の最終的な目標は、西洋医学が対処する炎症という「結果」を抑えるだけでなく、病気が発症した「体質の土壌」そのものを改善し、再発しにくい体へと導くことです。その実現のための主要な柱が、「鍼灸」による内側からの機能調整と、日々の「養生(食事・生活)」による持続的なサポートです。
自己回復力を高める鍼灸治療のメカニズム
鍼灸治療は、全身の「気・血・水」の流れを調整することで、患者様が本来持っている自己回復力(自然治癒力)を最大限に引き出します。これは、弱った内臓にエネルギー(気)を送り込み、消えかかった火種(自己治癒力)を、自力で燃え上がらせるための送風機のような役割を果たします。
- 全身機能の底上げと「肺—大腸」連携の回復: 鍼灸は単に痛い部分を治すのではなく、東洋医学で「根」と「葉」の関係にある肺(免疫・バリア機能)と大腸の連携を回復させます。これにより、大腸への過剰な負担が軽減されます。
- 経絡を通じた内臓への直接作用: ツボは内臓のSOSが体表に現れたものです。体表のツボを刺激することで、経絡(エネルギーの通り道)を通じて、弱っている脾(消化)、腎(生命力)、肝(血流・ストレス)などの内臓機能に直接働きかけ、バランスを整えます。
-
代表的なツボとその役割:
- 孔最(こうさい): 肺と深く関わり、粘膜のバリア機能や炎症を鎮める力を高めます。
- 大腸兪(だいちょうゆ): 背中にあり、大腸の機能を直接的に調整し、過敏な動きを落ち着かせる重要なツボです。
- 三陰交(さんいんこう): 婦人科疾患や消化器全般の血流改善、冷えの解消に用いられます。
- 周辺症状の同時改善: 鍼灸治療により、呼吸・循環・自律神経のバランスが根本から整うため、冷え性、生理痛、不眠(中途覚醒)など、これまでお悩みだった「全身の不調」も同時に軽減が見込めます。
鍼灸効果を最大化する再発予防の食養生と生活習慣
東洋医学では、「医食同源」の考えに基づき、食事は薬と同じくらい重要視されます。毎日腸に入る食べ物、そして日々の習慣を変えることで、炎症体質を根本から洗い流し、体質という古いOS(オペレーティングシステム)を、最新の強固なバージョンにアップデートします。
- 食事の基本姿勢:和食中心・温かい調理へ: 「消化に負担をかけず、体を冷やさない」ことが鉄則です。冷蔵庫から出した冷たいものや生食を控え、火を通した温かい食事で消化器官を労り、脾胃(消化力)の火を守りましょう。
- 推奨される食材の積極的な導入: 玄米、みそ汁、納豆、のり、小魚、海藻、根菜など、「ひらがなの食べ物」(日本の伝統食)を意識して取り入れます。これらは消化が良く、腸を修復する力をサポートします。
- 制限品との付き合い方(9割の法則): 小麦・砂糖・脂質などは炎症を誘発するため、完全に避けるのが理想です。しかし、無理な制限はストレスになるため、嗜好品として全体の1割程度にとどめる「無理のない制限」を続けることが、治療の成功に繋がります。
- 症状別のお助け食材: 肺を助ける白い食材(大根・蓮根)は粘膜の保護に役立ち、穏やかな辛味(生姜・大根のおろしなど)は血行や気の巡りを促し、炎症で滞った状態を改善します。
- 日常の冷え対策の徹底: 入浴はシャワーで済ませず、湯船にしっかり浸かって体の芯まで保温しましょう。足元や腹部を冷やさない服装を心がけることが、再燃の一因である「冷え(脾陽の低下)」を防ぎます。

潰瘍性大腸炎の治療戦略:西洋医学と東洋医学の「二本柱」による併用効果と連携の重要性
潰瘍性大腸炎(UC)の長期的な治療において、西洋医学と東洋医学は対立するものではなく、お互いの弱点を補い合う強力な「二本柱」となります。西洋医学の迅速な鎮火力と、東洋医学の根本的な体質改善力を組み合わせることが、症状の安定(寛解)への最も安定した近道です。
- 活動期(炎症が激しい時期)は「緊急消火」を最優先: 症状が激しい活動期は、病院の対症療法(薬物治療)による迅速な「緊急消火活動」が不可欠です。西洋医学は、火災現場へ急行する専門の消防隊のような役割を果たします。この期間も鍼灸や漢方は並行して行えますが、主治医の先生との連携をしっかり取りながら、「体質改善」の準備を水面下で強化します。
- 寛解期は「再燃しにくい強固な土台」を築く: 西洋医学の薬が炎症を一時的に鎮めている間に、東洋医学の鍼灸と養生(食事・生活習慣)を「車の両輪」として回し、根本的な体質の偏り(湿熱や脾腎の弱り)を是正します。これは、大規模火災の跡地を、次に火事が起きにくい耐火性の高い地盤に入れ替える、持続的で根本的な作業に相当します。
- 薬の減量と安定した寛解維持へ: 東洋医学的なアプローチによりご自身の自然治癒力(自己免疫調整力)が高まれば、長期的に依存してきた薬の量を減らせる可能性が高まります。体質が根本的に改善されることで、薬に過度に頼らず、健康で安定した生活を送るための土台が整います。最終的な目標は、外部サポートなしで自立運転できる体に移行することです。
- 主治医と鍼灸師・漢方医との連携が鍵: 併用治療の成功には、情報共有と相互理解が不可欠です。西洋医学の治療経過(炎症反応、内視鏡所見など)を東洋医学の専門家に伝え、東洋医学での体質変化(症状の軽減、生活習慣の改善度など)を主治医に共有することで、より的確な治療計画を立てることができます。
【結論】 潰瘍性大腸炎の治療は、どちらか一方を選ぶ「二者択一」ではありません。西洋医学で炎症を抑えながら、東洋医学で体質を強化する「統合医療」こそが、この難病を乗り越え、真の健康を取り戻すための最も現実的な戦略であると言えます。

潰瘍性大腸炎の鍼灸・漢方専門施術の料金と効果的な通院ペースについて
当院の潰瘍性大腸炎に対する根本治療は、患者様一人ひとりの「証(体質)」に基づき、鍼灸治療を行うオーダーメイドの施術です。自由診療(保険外)となりますが、再燃予防と寛解維持という長期的な視点での費用対効果を重視しています。
初回カウンセリング+施術
初回は詳細な問診(体質チェック)と東洋医学的な診断(脈診・舌診など)に時間をかけ、最適な治療計画を立案します。
2回目以降(通常施術)
症状の安定と体質改善を目標に、その日の体調と「証」の変化に合わせて鍼灸・手技を行います。
効果を最大化する通院ペースの目安(再燃予防の戦略)
- 活動期(症状が激しい時期): 週に1~2回の集中治療が必要です。炎症の「緊急鎮火」を側面からサポートし、「湿熱」を早期に排出します。
- 寛解導入期(症状が落ち着いてきた時期): 週に1回のペースで、弱った「脾胃」や「腎」といった内臓機能を根本から立て直します。
- 寛解維持期(安定期): 症状が完全に安定したら、2〜3週間に1回、あるいは月に1回のペースで、体質をチェックし、再燃の兆候を早期に摘み取る予防的メンテナンスを行います。
体質改善はダムの建設に似ており、最初は集中的な作業(通院)が必要ですが、完成後は少ないメンテナンス(予防的通院)で長期安定します。まずは集中的に通院し、早期に安定した寛解を目指しましょう。

院長プロフィール

中村 麻人(なかむら あさと)
札幌「東洋中村はり灸院」院長・鍼灸師。
「森を見て木を治す」東洋医学の視点で、肩こり、腰痛をはじめ、生理痛・顔面神経麻痺・潰瘍性大腸炎・耳管開放症など病院で原因不明、治療法がない慢性疾患を中心にはり治療を行っています。