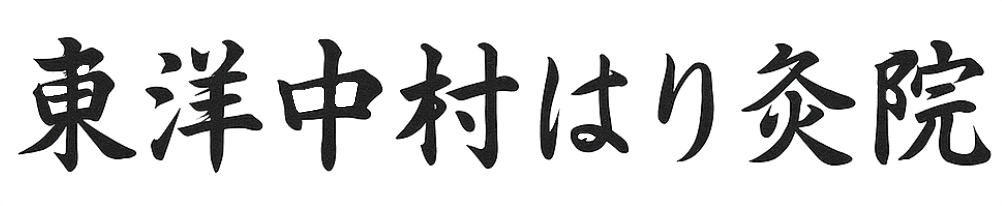線維筋痛症の激しい慢性痛を緩和
全身の痛みは「不通則痛(巡りの滞り)」と「神経の過敏化」のサインです。
肝と血の流れを整え、全身の気の渋滞を解消する鍼灸で、からだ全体からやさしく改善へ。
痛みの閾値を下げ、日常の疲労と不安を取り除きます。
本ページの内容(目次)
原因不明の全身痛を、東洋医学の視点から「不通則痛(滞り)」という根本原理で捉え、痛みの閾値を下げる体質改善の道筋を解説します。
線維筋痛症(FM)の概要と症状:「不通則痛」による全身の激痛
線維筋痛症は、全身の広範囲または特定部位に原因不明の慢性的な強い痛みが持続する病態です。東洋医学では、これは全身の「気・血・水」の巡りが極度に滞り、「不通則痛(通じざれば則ち痛む)」という激しい痛みが絶えず起こっている状態と捉えます。 まるで、全身の経絡という「気のパイプ」が冷えやストレスで細くなり、栄養(血)が詰まってしまったような状態です。
概要:慢性疲労と気の滞り
- 全身または一部に強い慢性痛が出現:痛みの部位が移動するのは、気の滞り(気滞)が全身の経絡を巡っているサインです。
- 20〜60代女性に多い傾向:婦人科疾患同様、血の滞り(瘀血)や肝(ストレス)の負担が関わるため、女性に多い傾向があります。
- 気候・天候で増悪:湿気(湿邪)や寒暖差(風寒の邪)といった外部の邪気に対して、体表のバリア(衛気)が弱いため、痛みがぶり返しやすいです。
主症状・重症化:全身の機能停止
- 激しい痛み、こわばり、強い倦怠感:痛みは常に体力を消耗させ、気(エネルギー)が底をついた気虚の状態にあります。
- 髪が触れるだけで激痛(アロディニア):神経が極度に過敏化しています。東洋医学では、全身の巡りの滞りによって痛みの閾値が極端に下がっている状態です。
- 精神・睡眠:痛みと不眠が**心(しん)や肝(かん)を疲弊させ、不眠、不安、抑うつといった自律神経の乱れの症状が強く出ます。
- 診断の目安:痛みが3ヶ月以上の持続することで線維筋痛症が疑われます。
併発・随伴症状:瘀血と五臓の虚弱のサイン
多くの症状を併発するのは、線維筋痛症が全身の体質的な病であることを示しています。
- 血の滞り(瘀血):めまい、冷え性、眼精疲労、肩こり、頭痛、生理痛、子宮内膜症など、血流の悪さが関わる症状を併発しやすいです。
- 五臓の虚弱:爪の不調(肝)、鼻炎・花粉症(肺)、便秘(大腸・脾胃)、高血圧(肝・腎)など、全身の臓腑の連携不全が症状として現れています。
西洋医学の見解と課題:「痛み」の根本原因へのアプローチ
線維筋痛症は、「器質的異常が見当たらない」という点で、西洋医学が最も困難に直面している疾患の一つです。
現状と痛みへの見解
西洋医学では、痛みの原因を主に中枢神経系(脳)に求めます。
- 原因不明:血液検査や画像診断で異常が見つからないことが多く、「器質的異常がない」とされます。
- 脳の誤作動仮説:痛みを伝える神経回路が過敏になり、脳が痛みを過剰に増幅して感じている(中枢性感作)という仮説が有力視されています。
- 根治法は未確立:西洋医学の多くは痛みの伝達を遮断するアプローチであり、対症療法が中心です。
治療と限界:全体像の欠如
西洋医学の治療は、痛みの信号そのものを抑制するものが主となります。
- 薬物療法:強力鎮痛薬に加え、脳の神経伝達物質に作用する抗うつ薬、抗てんかん薬、睡眠薬などが使用されます。
- 鎮痛効果の限界:一般的な鎮痛薬であるロキソニンや、モルヒネなどのオピオイドは、線維筋痛症の痛みに効果が乏しいとされることが多いです。
- 根本改善の難しさ:薬は症状の抑制を目的とするため、痛みを生み出す全身の体質や血流の悪さといった根本的な改善には至りにくいという課題があります。
- 臓器別診療の壁:全身の症状が多岐にわたるため、臓器別に科が分かれ、患者の全身の不調を統合的に捉えることが難しい場合があります。
東洋医学の捉え方:「不通即痛」と全身の「気の渋滞」
線維筋痛症の全身を襲う激痛は、全身の経絡(気の通り道)が冷えやストレスで滞り、神経が栄養不足と過敏状態に陥っているために起こります。
痛みの原則:不通即痛(通じざれば則ち痛む)
痛みの原理はシンプルです。巡りが滞ると、身体はそれをSOSとして「痛み」で伝えてきます。
- 不通即痛:気(エネルギー)、血(栄養)、水(体液)の巡りが途絶えたり、滞ったりすることで痛みが生じます。
- 痛みは“流れの悪さ”のサイン:全身を襲う痛みは、「全身の気の流れが悪く、栄養が末端まで届いていない」という根深い体質の乱れを知らせる身体のサインです。
根本原因:肝の機能低下と瘀血(おけつ)体質
全身の巡りの滞りには、主に「肝(かん)」の機能と「瘀血(おけつ)」が関わります。
- 血の巡りを司る肝の低下がベース:肝は全身の気血をスムーズに巡らせる役割を担う司令塔です。過度なストレスや疲労で肝の疎泄(そせつ:巡らせる働き)が落ちると、全身の気の渋滞が起こります。
- 瘀血(おけつ):停滞した汚れた血が全身を巡りにくくしている状態です。線維筋痛症では、この瘀血傾向が非常に強いことが多く、血虚(栄養不足)と瘀血が混在しています。
- 自律神経の乱れ:我慢やストレスで肝の疎泄が落ちることで、自律神経の過緊張を引き起こし、血管が細くなり、全身に滞り(不通)が生じて激痛へと繋がります。
鍼灸による改善方法(経絡治療):全身の「気の渋滞」を解消する
線維筋痛症の治療は、「不通則痛」を解消し、神経が過敏に反応する体質を根本から変えることが目標です。鍼灸は、全身の経絡を優しく調整することで、脳の痛みの増幅(中枢性感作)を鎮静化させます。
全身の通りを整える本治法:痛みへの敏感さを下げる
- 経絡に優しく刺激し、気・血・水の流れを回復:全身の「気の渋滞」や「血の滞り(瘀血)」を解消し、全身の経絡をスムーズに通します。
- 五臓(肝・脾・腎)の働きを整え、痛みの根本へ:特にストレスを司る肝や、生命力・ホルモンを司る腎の働きを整え、痛みの発生源を断ちます。
- 関連ツボ例:三陰交(血流改善・婦人科)、外関(気の流れ)、足臨泣(側頭部の痛み・自律神経)、陽陵泉(筋の緊張緩和)など、全身の調整ツボを個別の体質に合わせて選びます。
安全な保存療法/西洋医学との併用
- 痛くない鍼・熱くないお灸で安心:線維筋痛症の患者様は神経が過敏なため、体に負担や緊張を与えないやさしい刺激を徹底します。
- 副作用の懸念が少ない:薬のような依存性や胃腸への副作用が少なく、体本来の調整力を引き出すため、年齢を問わず安心して受けられます。
- 併用:病院の対症療法(痛み止め)で症状を抑えつつ、鍼灸で根本の体質改善を並行して進めることが、最も効率的な改善への道です。
- 随伴症状も同時改善:頭痛・冷え・便秘・生理不順など、痛みの背景にある全身の不調も、体質を整えることでまとめて改善に向かいます。
料金について
初回:5,500円(税込)
2回目以降:5,000円(税込)
院長プロフィール

中村 麻人(なかむら あさと)
札幌「東洋中村はり灸院」院長・鍼灸師。
「森を見て木を治す」東洋医学の視点で、肩こり、腰痛をはじめ、生理痛、顔面神経麻痺、潰瘍性大腸炎、線維筋痛症、耳管開放症など、病院で原因不明・治療法がない慢性疾患を中心に経絡治療を行っています。