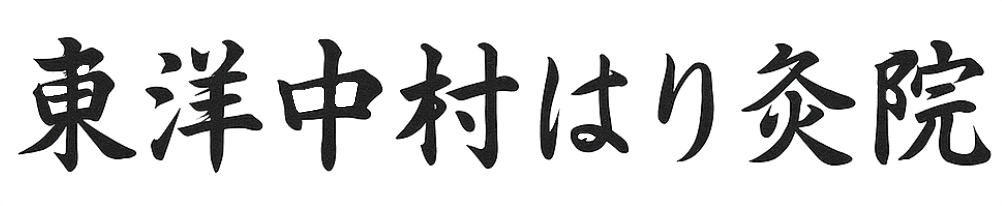過敏性腸症候群(IBS)を根本から安定へ
IBSは「繊細な心(肝)」と「冷えて弱い腸(脾胃)」の機能のミスマッチで起こります。
過剰なストレス反応という悪循環を断ち切り、「気の巡り」と「腸の火力」を立て直す。
不安を自信に変える、自律神経のリズム調整と、やさしい経絡治療で、外出を諦めない日常へ導きます。
本ページの内容(目次)
IBSを「気の滞り」という観点から捉え、過剰に敏感な腸と心を根本から安定させるための具体的な道筋を解説します。
過敏性腸症候群(IBS)の概要と有病率
過敏性腸症候群(IBS)は、内視鏡などで見ても腸に炎症や潰瘍といった「器質的な異常がない」にもかかわらず、腹痛やガス、下痢・便秘が数カ月以上にわたって続く慢性疾患です。まるで、繊細な神経が腸の動きを過剰に操作しているかのように、ストレスや不安が直接症状に結びつきます。
先進国に多く、日本国内でも約10人に1人がこの症状に悩んでいると言われます。思春期〜20〜30代の若い世代に目立ち、通勤・通学、会議、人前での発表など、日常生活の質(QOL)を著しく下げてしまうのが最大の特徴です。
IBSが生活にもたらす主な苦痛
- 通勤・通学途中の突然の腹痛:緊張やストレスが引き金となり、急に便意や激しい腹痛に襲われ、外出が億劫になります。
- 電車や人前での不安、ガス溜まりによる張り:お腹の調子を常に気にし、「もし症状が出たらどうしよう」という予期不安が、さらに腸の過敏性を高める悪循環に陥ります。
- 下痢と便秘を繰り返す:症状が不安定で、一貫性のない腸の動きに振り回され、トイレが手放せない感覚(裏急後重など)に苦しみます。
西洋医学のIBS診断基準(ローマⅣ基準):「病気ではない」という定義の限界
西洋医学では、過敏性腸症候群(IBS)を診断するために、世界的に使われている「ローマⅣ基準」という詳細なガイドラインがあります。これは、「病変がないのに症状が続く」という状態を明確に定義し、区別するための基準です。
- 大腸に器質的な病変がないことが前提:まず、潰瘍や炎症、がんなどの「目に見える異常」がないことを確認します。この点が、東洋医学が目指す「機能的なバランスの回復」の出発点となります。
- 最近3か月の間に月4日以上の腹痛が繰り返し起こる:腹部の不快感ではなく、痛みを伴うことが診断の重要な要素です。
-
腹痛が次の2つ以上に関連している:
- 排便で症状が軽くなる:便が排出されることで、腸の緊張が一時的に緩むことを示します。
- 排便頻度が変化する:急に増えたり(下痢型)、極端に減ったり(便秘型)するなど、リズムが乱れている状態です。
- 便の形状・硬さが変化する:固い便(便秘)と軟らかい便(下痢)が混在するなど、腸の動きが不安定であることを示します。
- 【診断の期間】 上記の症状が3か月以上継続し、かつ6か月前から同様の症状がある場合に、IBSと診断されます。
【東洋医学の立場】この診断基準は、検査で異常が見つからない患者様を救うものですが、IBSを「ストレスによる機能的な問題」として片付けてしまいがちです。東洋医学では、この「機能的な異常」こそが、気の巡りの滞りや内臓の冷え(脾虚)という具体的な「体質的な異常」として捉え、根本から治療していきます。
西洋医学での原因の捉え方と治療の現状
西洋医学では、IBSを「機能的な問題」と位置づけ、その背景には複数の要因が複雑に絡み合っていると考えます。しかし、その治療は、あくまでも症状の緩和が中心となるため、根本的な解決に至らないケースが多く見られます。
考えられる要因(IBSが起きる背景)
目に見える炎症はないものの、腸の過敏性(敏感さ)を高めている様々な原因が指摘されています。
- 食物不耐症:特定の食べ物(乳製品・グルテン・果糖など)が消化されにくく、腸内でガス発生や腹痛を引き起こします。東洋医学でいう「湿」や「飲」の原因です。
- 小腸内細菌異常増殖症(SIBO):小腸内で細菌が異常に増えることで、ガスが多量に発生し、腹部の張りや不快感を招きます。
- ストレス・感染後腸症候群:「脳と腸の相関関係」が重視され、ストレスや過去の感染症(胃腸炎など)が、腸の神経を過敏にした状態が続くと考えられています。
- 腸内フローラの乱れ:善玉菌と悪玉菌のバランスが崩れ、腸のバリア機能が低下し、過敏性が増しています。
治療の現状と限界
西洋医学の治療は、「今出ている症状を抑えること」に焦点を当てた対症療法が中心となります。
- 対症療法:整腸剤、下痢止め、便秘薬、腸の動きを調整する薬などが使われます。また、「脳と腸の関係」に働きかけるために、抗うつ薬や抗不安薬などが用いられることもあります。
- 根本治療へのアプローチの限界:これらの薬は、急な腹痛という「目の前の火」を鎮めるには有効ですが、体質そのものの過敏性や、ストレスへの弱さという「火種」を取り除くことはできません。
- 東洋医学の出番:西洋医学で改善しないのは、「気の滞り(ストレス)」「脾胃の冷えと弱さ」という東洋医学的な根本原因が残っているためです。当院では、この体質そのものに鍼灸でアプローチします。
東洋医学から見たIBS:全身の気の乱れを捉える
西洋医学で「ストレス」と一括りにされるIBSですが、東洋医学では、それを「気の滞り(肝気鬱結)」や「消化機能の低下(脾虚)」という具体的な体質の偏りとして捉えます。「腸の暴走」は、全身のバランスが崩れた結果なのです。
A. IBSの根っこにある「気の滞り」体質チェック
IBSの症状を持つ方は、腸だけでなく、自律神経や感情を司る「肝(かん)」の機能が過敏になっていることが多いです。以下の項目は、その「気の滞り」を反映しています。6つ以上当てはまる方は、特に鍼灸治療が適しています。
- 下痢や便秘しやすい:腸の動きが不安定で、気の巡りの乱れが直接排泄機能に影響しています。
- ガスが溜まり、お腹が張りやすい:「気」がスムーズに流れないため、お腹で停滞し、張りを生じます。(まるで風船のようにガスがパンパンになる状態)
- 末端が冷える:気の力で温かい「血」が末端まで届きにくくなっています。
- 不安感や考え事が多い:「脾(ひ)」が過剰な思考によって疲弊し、気の生成が低下しています。
- 気分が落ち込みやすい:「肝」の気の流れが詰まり、感情がうまく発散できていません。
- 爪に縦線が入っている:「肝」は爪の状態に現れやすく、気の消耗や血行不良を示します。
- 頭痛が出やすい:気の滞りが頭部まで上昇し、血管や神経を圧迫します。
- 朝が弱い、寝つきが悪い:気の乱れが自律神経を興奮させ、睡眠の質を低下させています。
- 人に気を遣いすぎる:常に気を張り、「肝」に大きなストレス負荷がかかっています。
- 力が抜きにくい:体が常に緊張しており、交感神経が優位な状態が続いています。
B. 東洋医学的なIBSの原因分類
- 原因:暴飲暴食や冷たい飲食などで、消化吸収の要である「脾胃」の機能が低下し、腸が冷えて弱っている状態です。
- 併発:食欲不振、疲労倦怠感、食後の下痢、むくみ、冷え。
- 例え:燃費が悪いストーブのように、消化の火力が弱まっているため、食べ物をうまく温めて処理できていません。
- 原因:ストレスや精神的負担で、「肝」が司る気の巡りが滞り、その乱れた気が腸を過敏に刺激しています。
- 併発:ため息、ゲップ、イライラ、お腹の張り(ガス)、動悸、緊張による腹痛。
- 例え:情緒不安定な運転手(肝)が、アクセルとブレーキ(腸の動き)を交互に踏みつけているような状態です。
東洋医学アプローチの利点:IBSの悪循環を断ち切る
IBSの根本原因は、「ストレスに弱い体質」と「機能が低下した腸」の悪循環にあります。東洋医学の鍼灸治療は、この悪循環の鎖を断ち切り、薬に頼らない安定した日常を取り戻すための、本質的な利点を提供します。
- 全身の体質を根本から整える:薬が「腸の動き」だけを操作するのに対し、鍼灸は腸だけでなく、その背景にある「気の滞り」や「脾胃の冷え」といった全身の体質を改善します。これは、土壌の質そのものを良くすることに繋がり、症状が再燃しにくい強固な土台づくりを実現します。
- 全身の不調を同時にケア:IBSで現れる頭痛・肩こり・生理痛・中途覚醒といった便通以外の悩みは、すべて気の乱れや血行不良という同じ根っこから生じています。体質を整えることで、これらの周辺症状も玉突き式に軽減が見込めます。
- 経絡治療によるやさしい鍼灸:IBSの患者様は神経が過敏なため、強い刺激は逆効果です。当院の経絡治療は、「痛くない、熱くない」やさしい刺激を心がけており、体がリラックスして副交感神経が優位になるため、心身ともに負担なく継続しやすいのが特徴です。
- 日常生活に落とし込める具体的なアドバイス:治療院での施術効果を持続させるため、一人ひとりの体質に合わせた食事(食養生)や、冷え・睡眠に関する具体的なアドバイスを指導します。生活習慣そのものを味方につけることで、安定した状態を自分で維持できるようになります。
ご予約はこちら
院長プロフィール

中村 麻人(なかむら あさと)
札幌「東洋中村はり灸院」院長・鍼灸師。
「森を見て木を治す」東洋医学の視点で、肩こり・腰痛をはじめ、生理痛・顔面神経麻痺・潰瘍性大腸炎・耳管開放症など病院で原因不明、治療法がない方を中心にはり治療を行っています